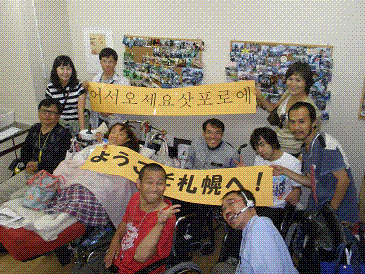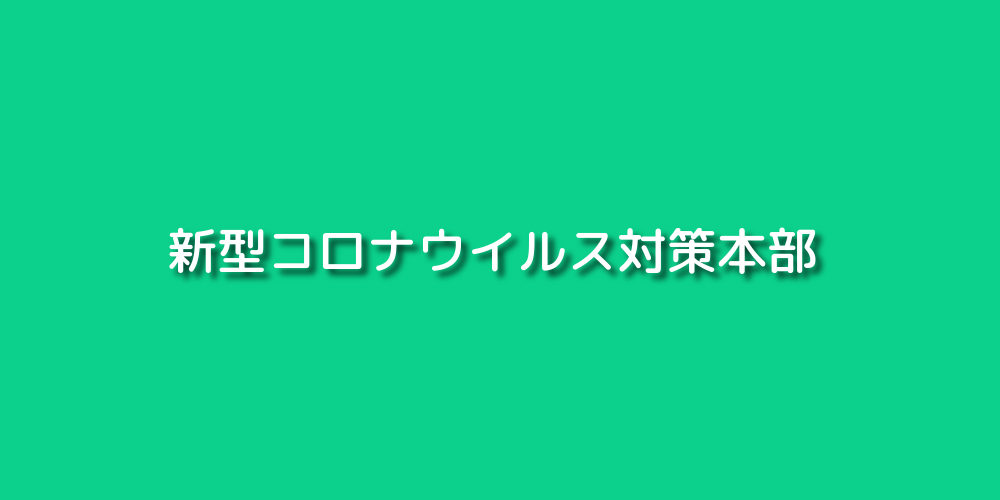Blog Archives
CILラピタ
センター基礎情報
| 代表者名 | 佐藤祐 |
|---|---|
| 副代表者名 | |
| 事務局長名 | |
| 障害者人数 | 障害者スタッフ 1名 (肢体 1 ) |
サービス実施状況
| サービス事業名 | 実施状況 | 実施事業名 | 受託状況 |
|---|---|---|---|
| 相談事業・情報提供 | ○ |
居宅介護 | ○ |
| ピア・カウンセリング | ○ |
重度訪問介護 | ○ |
| 自立生活プログラム | ○ |
同行援護 | - |
| 自立生活体験室 | ○ |
行動援護 | - |
| 介助者派遣サービス | ○ |
重度障害者等包括支援 | - |
| 移送サービス | - |
生活介護 | - |
| 権利擁護 | ○ |
共生型サービス | |
| 介護保険指定事業 | |||
| 居宅介護支援事業 | |||
| 就労移行支援 | |||
| 就労継続支援A型 | - |
||
| 就労継続支援B型 | - |
||
| 就労定着支援 | |||
| 共同生活援助(グループホーム) | - |
||
| 自立生活援助 | |||
| 地域移行支援 | - |
||
| 地域定着支援 | - |
||
| 計画相談支援 | - |
||
| 基幹相談支援センター(委託) | |||
| 移動支援(地域生活支援事業) | ○ |
||
| 地域活動支援センター | |||
| 重度訪問介護利用者の大学修学支援事業 | |||
| 喀痰吸引等の登録研修機関 | - |
||
| 喀痰吸引等の登録特定行為事業者 | - |
||
| 障害者虐待防止センター | - |
||
| 福祉有償運送(移送サービス) | - |
||
センターの概要
歴史的背景
北海道旭川は代表の佐藤が、養護学校(小・中学校)に併設した施設で過ごした地域である。重度の障害者は施設か家族介護という仲間が多く、情報があっても自立生活を選ぶことができにくいという現状を変えたいとの思いから、2013年全国広域協会・推進協会の支援を得て、CIL研修、全国の多様な研修をかさねて、2014年旭川にCILラピタを設立。
特色
設立以来の運動体としての実績
今度目指すもの
| 北海道北部の旭川地域を拠点に全国とつながりながら、重度障害者の介護保障、障害の社会モデルを軸に障害者運動を北海道に広め進めていきたい。
北海道の全市町村であたりまえに重度障害者が暮らしたい街で自立生活をできるよう活動していきたい。 |
自立生活センター北見
センター基礎情報
| 代表者名 | 渡部 哲也 |
|---|---|
| 副代表者名 | |
| 事務局長名 | |
| 障害者人数 | 障害者スタッフ 4名 (肢体 4 ) |
サービス実施状況
| サービス事業名 | 実施状況 | 実施事業名 | 受託状況 |
|---|---|---|---|
| 相談事業・情報提供 | ○ |
居宅介護 | ○ |
| ピア・カウンセリング | ○ |
重度訪問介護 | ○ |
| 自立生活プログラム | ○ |
同行援護 | - |
| 自立生活体験室 | ○ |
行動援護 | - |
| 介助者派遣サービス | ○ |
重度障害者等包括支援 | - |
| 移送サービス | - |
生活介護 | - |
| 権利擁護 | ○ |
共生型サービス | - |
| 介護保険指定事業 | - |
||
| 居宅介護支援事業 | - |
||
| 就労移行支援 | - |
||
| 就労継続支援A型 | - |
||
| 就労継続支援B型 | - |
||
| 就労定着支援 | - |
||
| 共同生活援助(グループホーム) | - |
||
| 自立生活援助 | - |
||
| 地域移行支援 | ○ |
||
| 地域定着支援 | ○ |
||
| 計画相談支援 | ○ |
||
| 基幹相談支援センター(委託) | - |
||
| 移動支援(地域生活支援事業) | - |
||
| 地域活動支援センター | - |
||
| 重度訪問介護利用者の大学修学支援事業 | - |
||
| 喀痰吸引等の登録研修機関 | ○ |
||
| 喀痰吸引等の登録特定行為事業者 | ○ |
||
| 障害者虐待防止センター | - |
||
| 福祉有償運送(移送サービス) | - |
||
センターの概要
歴史的背景
自分が知己で生きていくことが難しいと感じ、何かないだろうかと探していた時に知人から全国障害者介護保障協議会・自薦ヘルパー(パーソナルアシスタント制度)推進協会を教えてもらい、指導と協力いただき、今にいたります。
特色
代表者がALS当事者なので、全国のALS当事者、家族、介護職の人たちに自立生活について、発信している。その中でもコミュニケーションの大切さなどに力をいれていて、講演講師も引き受けています。重度の当事者には、最初しばらくの間は訪問して個別ピアカン、個別ILP、自立に向けて時間をかけています。
設立以来の運動体としての実績
ALSの24時間交渉
脳性麻痺の女性の24時間交渉(施設を退所するときは区分3だった)
最寄りの無人駅での乗車交渉
差別解消法施行から毎年街頭パレード
喀痰吸引の登録手数料の撤廃運動 など
今度目指すもの
今後も施設で暮らす障がい当事者が地域で暮らせるための自立支援。
差別解消法の周知運動
誰もが住みやすい地域にしていくために、権利擁護活動
NPO自立生活センターハンズ帯広
センター基礎情報
| 代表者名 | 吉澤 一廣 |
|---|---|
| 副代表者名 | |
| 事務局長名 | 菅原 雅江 |
| 障害者人数 | 障害者スタッフ 2名 (肢体 1 その他 1 ) |
サービス実施状況
| サービス事業名 | 実施状況 | 実施事業名 | 受託状況 |
|---|---|---|---|
| 相談事業・情報提供 | ○ |
居宅介護 | ○ |
| ピア・カウンセリング | ○ |
重度訪問介護 | ○ |
| 自立生活プログラム | ○ |
同行援護 | ○ |
| 自立生活体験室 | ○ |
行動援護 | - |
| 介助者派遣サービス | ○ |
重度障害者等包括支援 | - |
| 移送サービス | ○ |
生活介護 | ○ |
| 権利擁護 | - |
共生型サービス | |
| 介護保険指定事業 | |||
| 居宅介護支援事業 | |||
| 就労移行支援 | |||
| 就労継続支援A型 | - |
||
| 就労継続支援B型 | - |
||
| 就労定着支援 | |||
| 共同生活援助(グループホーム) | - |
||
| 自立生活援助 | |||
| 地域移行支援 | - |
||
| 地域定着支援 | - |
||
| 計画相談支援 | ○ |
||
| 基幹相談支援センター(委託) | |||
| 移動支援(地域生活支援事業) | ○ |
||
| 地域活動支援センター | |||
| 重度訪問介護利用者の大学修学支援事業 | |||
| 喀痰吸引等の登録研修機関 | - |
||
| 喀痰吸引等の登録特定行為事業者 | - |
||
| 障害者虐待防止センター | - |
||
| 福祉有償運送(移送サービス) | ○ |
||
センターの概要
歴史的背景
(社団)帯広身体障害者福祉協会車椅子部会がオベリベリ市民センターを1956年に設立。NTVからの車両の贈呈を受けて、送迎事業をした。その後、その送迎事業を更に発展解消してNPO自立生活センターへと進み設立の運びとなった。 その後、財団法人よりリフトバス1台を贈呈され、移動支援を広げた。
特色
十勝一円から重度障害者の相談事業については事業所より代表が訪問して取り組んでいます。
設立以来の運動体としての実績
1,代表は、長年、「まちづくり」にとりくみ、帯広市福祉環境整備要項の起案等制度作成に参加し、制定した帯広駅のバリアフリー化実現の実績を持つ。
2,現在も歩道等の整備に取り組んでいる。 市道の計画や不備についての提言
今度目指すもの
帯広市のみならず、十勝地域全体の福祉環境改善運動に取り組む。また、障害当事者の壁を取り除く運動を続け、協同して闘いを推進したい!
自立生活センター・IL-ism
センター基礎情報
| 代表者名 | 花田 貴博 |
|---|---|
| 副代表者名 | |
| 事務局長名 | 白水 美江子 |
| 障害者人数 | 障害者スタッフ 0名 ( ) |
サービス実施状況
| サービス事業名 | 実施状況 | 実施事業名 | 受託状況 |
|---|---|---|---|
| 相談事業・情報提供 | - |
居宅介護 | - |
| ピア・カウンセリング | - |
重度訪問介護 | - |
| 自立生活プログラム | - |
同行援護 | - |
| 自立生活体験室 | - |
行動援護 | - |
| 介助者派遣サービス | - |
重度障害者等包括支援 | - |
| 移送サービス | - |
生活介護 | - |
| 権利擁護 | - |
共生型サービス | |
| 介護保険指定事業 | |||
| 居宅介護支援事業 | |||
| 就労移行支援 | |||
| 就労継続支援A型 | - |
||
| 就労継続支援B型 | - |
||
| 就労定着支援 | |||
| 共同生活援助(グループホーム) | - |
||
| 自立生活援助 | |||
| 地域移行支援 | - |
||
| 地域定着支援 | - |
||
| 計画相談支援 | - |
||
| 基幹相談支援センター(委託) | |||
| 移動支援(地域生活支援事業) | - |
||
| 地域活動支援センター | |||
| 重度訪問介護利用者の大学修学支援事業 | |||
| 喀痰吸引等の登録研修機関 | - |
||
| 喀痰吸引等の登録特定行為事業者 | - |
||
| 障害者虐待防止センター | - |
||
| 福祉有償運送(移送サービス) | - |
||
センターの概要
歴史的背景
2004年の秋に新たなCILを作ろうという気運が高まり、設立の準備が始まった。そして2005年4月1日に任意団体として障害者自立生活センターIL-ismを設立、同年7月にNPO法人格を取得した。
特色
・当事者スタッフに人工呼吸器使用者がいることから人工呼吸器を使用し、医療的ケアの必要な障害を持つ方への介助者派遣を行っている。また人工呼吸器に関する情報提供と研修も行っている。
・施設入所者等に対する個別ILPを施設内で実施している。
設立以来の運動体としての実績
・公共交通機関とバリアフリー化に向けた話し合いを行い、できるところから改善してもらう関わりを続けている。
今度目指すもの
<運動>
・個別の障害に応じた支給決定の仕組みづくり
・PAを含めたヘルパー制度の介助内容制限の拡大
・PA制度における直接雇用契約の実現
<活動>
・若手、障害当事者との交流
・ILP,ピアカウンセリング講座の充実
・ベンチレーター使用者に対する支援の強化、全国ネットワークの強化
・ホームページの充実
自立生活センター・さっぽろ
センター基礎情報
| 代表者名 | 佐藤 きみよ |
|---|---|
| 副代表者名 | |
| 事務局長名 | 岡本 雅樹 |
| 障害者人数 | 障害者スタッフ 6名 (肢体 6 ) |
サービス実施状況
| サービス事業名 | 実施状況 | 実施事業名 | 受託状況 |
|---|---|---|---|
| 相談事業・情報提供 | ○ |
居宅介護 | ○ |
| ピア・カウンセリング | ○ |
重度訪問介護 | ○ |
| 自立生活プログラム | ○ |
同行援護 | ○ |
| 自立生活体験室 | - |
行動援護 | - |
| 介助者派遣サービス | ○ |
重度障害者等包括支援 | - |
| 移送サービス | - |
生活介護 | - |
| 権利擁護 | ○ |
共生型サービス | - |
| 介護保険指定事業 | - |
||
| 居宅介護支援事業 | - |
||
| 就労移行支援 | - |
||
| 就労継続支援A型 | - |
||
| 就労継続支援B型 | - |
||
| 就労定着支援 | - |
||
| 共同生活援助(グループホーム) | - |
||
| 自立生活援助 | - |
||
| 地域移行支援 | ○ |
||
| 地域定着支援 | ○ |
||
| 計画相談支援 | ○ |
||
| 基幹相談支援センター(委託) | - |
||
| 移動支援(地域生活支援事業) | ○ |
||
| 地域活動支援センター | - |
||
| 重度訪問介護利用者の大学修学支援事業 | - |
||
| 喀痰吸引等の登録研修機関 | ○ |
||
| 喀痰吸引等の登録特定行為事業者 | ○ |
||
| 障害者虐待防止センター | - |
||
| 福祉有償運送(移送サービス) | - |
||
センターの概要
歴史的背景
ベンチレーターを使用しながら24時間の介助を受け自立生活を営む代表の佐藤が2名の障害当事者の自立支援を行い、自立生活を始めたのち、医療ケアを提供できる介助者の育成・介助者派遣の必要性が高まったことや障害当事者同士の自立支援の必要性を感じ、自立生活センターの設立となった。またベンチレーターに関する情報提供とベンチレーター使用者等、最重度障害者の自立支援の必要性も設立の経緯のひとつとも言える。
特色
ベンチレーターを使用する当事者が中心となり、自立支援や情報提供を行っている。また、必要に応じ道外にも足を運び、ベンチレーターに関する講演会などを開催している。 地域のバリアフリーの飲食店やアミューズメント施設などを集めた小冊子を発行し、情報提供を行っている。
設立以来の運動体としての実績
1.自薦ヘルパーの制度化
2.24時間介助制度の実現
3.地下鉄駅・飲食店・大手百貨店のバリアフリー化
4.札幌市パーソナルアシスタンス制度の実現
今度目指すもの
<運動>
・2020年度からはじまる重度訪問介護における「非定型」支給決定の適切な運用を求める運動
・介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(特定の者)の登録手数料撤廃運動
・PA制度における直接雇用契約の実現
<活動>
・若手、障害当事者との交流
・地域社会との接点づくり
・ベンチレーター使用者に対する支援の強化