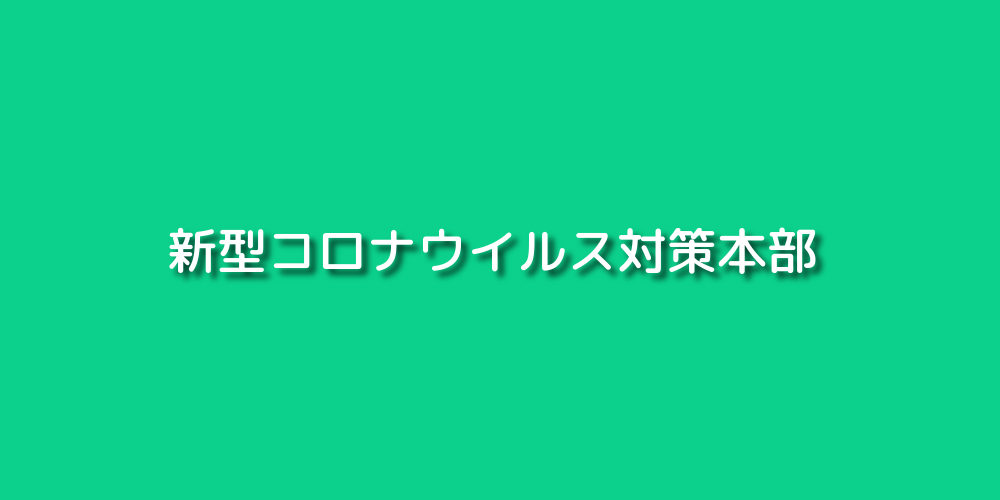Blog Archives
【イベント案内】5月21日(水)13:30「スミスの一日をのぞいてみよう」

この度、JILユース&ニューフェイスグループ主催にて、若手当事者向けの自立生活体験プログラム「スミスの一日をのぞいてみよう」をZoomにて開催する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。
お知り合いのご興味がおありの方へ、どうぞこの情報を共有してくださいますでしょうか。お願いします。
お申し込みは、以下のGoogleフォームからお願いします。
https://forms.gle/bQhDECEyJGv6UtzUA
●開催概要
イベント名:「スミスの一日をのぞいてみよう」
日時:2025年5月21日(水) 13:30-15:30
イベント概要:三宅貴大さん(あいえるの会/福島県郡山市)の一日を追ったビデオの放映と講話を通じ、地域生活に関心のある若い障害当事者と学び合い、対話を通じて交流を図る企画
講師:三宅貴大さん(あいえるの会/福島県郡山市)
本プログラムは、JIL北海道・東北ブロックを中心に、全国から広く参加者を募集しております。将来的には各ブロックでの定期開催を目指しています。
●情報保障:文字通訳提供あり
イベントチラシ(PDF):2505-smith
イベントチラシ(テキスト):2505-smith
「みちのく記念病院」の殺人隠蔽と不正問題
についての要望書
についての要望書
厚生労働大臣 福岡 資麿 殿
2025年3月27日
全国自立生活センター協議会
代表 平下耕三
東京都八王子市明神町4-11-11
シルクヒルズ大塚1F
「みちのく記念病院」の殺人隠蔽と不正問題についての要望書
平素は精神医療の改革を進めていただきありがとうございます。
私たちは障害種別を問わず障害者が地域であたりまえに自立生活が実現できるよう、障害者の権利擁護活動や様々な支援をおこなっている全国組織です。
各種メディアによって大々的に報道されていますが、青森県八戸市の「みちのく記念病院」で殺人事件隠蔽が明らかになり、理事長と主治医が逮捕されています。私たちは精神障害者が尊厳を踏みにじられることなく安全に医療を受ける権利が保障され、地域生活に戻れるよう以下の要望をさせていただきます。
1 「事件の徹底した調査と理事長、主治医などに対する処分について」
入院病棟で殺人があるということは病院としてあってはならない事件ですが、起こってしまった事件を隠蔽するということは、人の命を預かる病院・医師としてありえない行為であり、人としての道義も問われます。私たちはそのような医師に心身を預けることは到底出来ません。またそのような病院が存在すること自体が精神疾患を持ったものにとってはもちろん、社会にとっても大きな脅威になります。病院のそうした行為は精神障害者や精神科病院への偏見・差別を助長することになりますので徹底した調査と厳しい処分を求めます。
2 「不正防止のために病院の徹底した調査と、医師の資質に頼る精神医療システムの抜本的変革について」
担当の看護師は事件があってすぐに院長などに「外傷がある」と報告をしていたにも関わらず、主治医は次の日の朝まで出勤せず出勤後も診察を行いませんでした。その間の被害者への処置は看護師のみで行っておりました。被害者の死亡原因は頭蓋内損傷および失血であるのに、診断書を「肺炎」と書くよう院長が看護師に指示し、病院から遺族への説明では「ころんで容体が急変した」と伝えています。死亡診断書の担当医は事件当時同病院に認知症で入院中の医師の名前を使い作成しています。また現在服役中の男性を事件が外部にもれないようにするために医療保護入院に切り替え隔離したとされています。このように隠蔽は院長の指示の元、組織的に行われました。
隔離され閉鎖された病棟は外部から確認することが出来ず、医師の決定が絶対の権力となります。その決定は医師の資質・倫理観などに依存しています。このようなシステムでは、患者は精神医療の名のもとに簡単に人権が奪われる危険性があります。
今回の事件の徹底した調査と厳正な処分、また医師の資質によって簡単に事実を隠蔽できるような現精神科医療のシステムを抜本的に見直すように求めます。
3 「事件以外の病院内の不正に徹底した調査と再発防止について」
みちのく記念病院はこの事件以外にも200件以上同様な手口で認知症入院中の医師の名前を使い死亡診断書を作成し、そのほとんどが「肺炎」と記載していました。不正が常態化していた可能性が高く、組織ぐるみで不正を行っていた疑惑があります。病院内での調査ではなく、第三者委員会を設置し徹底した調査と再発防止策の検討をお願いします。
4 「みちのく記念病院の廃院について」
私たち精神障害者、また国民にとって脅威となるみちのく記念病院は廃院も含めて検討してください。
5 「石山隆容疑者と石山哲容疑者の指定医等の停止の要望」
元院長であり医療法人『杏林会』理事長の石山隆容疑者、担当主治医の石山哲容疑者は精神保健指定医の無期限の資格の停止、可能であれば医師免許の停止を強く希望します。
6 「精神疾患と身体疾患重複患者の受け入れ問題について」
精神科治療と身体疾患の重複の場合、多くの精神科病院あるいは一般の総合病院、身体疾患を専門とする病院では受け入れが出来ず、みちのく記念病院が最後の受け皿となって一手に引き受けていたとされます。故にこのような事件が起こると、そうした精神疾患・身体疾患の重複する患者を受け入れられる病院がなく、医療崩壊にすぐに陥ってしまいます。なによりそれは患者、市民にとって憲法で保障された、健康に生きる権利、その他の基本的人権を著しく脅かすことになり、生死にかかわる一大事であります。これは神戸市の神出病院での事件、八王子市の滝山病院事件などと酷似し、このようなケースは全国に多く存在すると推測されます。そうした現状が「悪い病院」であっても受け皿がなくなるので仕方がないと、問題解決がされないまま存続する可能性も高いと考えられ、同様の問題が起きないために抜本的な改革を検討してください。
7 「精神疾患・身体疾患の重複患者を受け入れる病院の実態調査」
精神疾患と身体疾患の重複する患者を受け入れる病院の実態調査を行い実態の把握と、問題の把握と解決を早急に行ってください。
8 「精神疾患・身体疾患の重複患者を受け入れる病院を増やすための取り組み」
精神疾患と身体疾患の重複する患者を受け入れる病院を増やすための取り組みを厚生労働省として取り組んでください。
9 「精神科病院内での事件を防ぐための措置と隔離拘束について」
精神科病院内で殺人が起こるようなことは決してあってはなりませんが、それを防ぐために患者を安易に隔離・拘束することは大いに問題があると思われます。服役している男性は「身体拘束が辛くて事件を起こせば病院から出られると思った」いう趣旨のことを話しており、問題の根本に、患者への人権侵害があり、そのことが事件を起こす大きな一因となったと考えられます。この事実を重く受け止め、国の方針として、隔離拘束を基本的になくし、患者に寄り添い、気持ちを聞くことによる治療を基本とすることを方針として明確化してください。安易な隔離・拘束をなくすためにさらなる基準の厳格化を求めます。
10 「殺人事件で精神障害への差別が助長されないための対処」
精神科に入院中の患者が別の患者を歯ブラシで刺して死亡させたという犯行の残忍性が強調された報道がされ、さらにアルコール依存症の患者が事件を起こしたという差別や偏見を煽るような誤った情報拡散も広まっています。依存症患者への偏見・差別、精神障害者全体への偏見と差別が強まることを私たちは危惧しています。厚労省として精神障害者の人権を守り差別を助長しないよう自治体への注意喚起、ACジャパンなどを通じてテレビなどで広報するなど、精神障害者への差別・偏見の防止策をしてください。
以上10項目について全国自立生活センター協議会は強く要望いたします。10項目の要望について5月31日までにご回答ください。宜しくお願い致します。
「みちのく記念病院」の殺人隠蔽と不正問題
についての要望書
【お知らせ】中西正司さんお別れ会
「中西正司さん お別れの会」のご案内
令和7年3月26日、日本のそして世界の自立生活運動のリーダーのひとりである中西正司さんが逝去されました。
障害者運動史に残るその功績を振り返りつつ、みなさんと一緒に故人を偲び語り合うお別れの会を下記のとおり開催いたします。お忙しいこととは存じますが、ご来場賜りますようお願い申し上げます。
日時: 4月26日(土) 10時~18時
会場: 京王プラザホテル八王子 4F 錦(にしき)
※上記時間内にご自由にお越し下さい。
長い活動の記録や事務所などでの写真、ゆかりある物や愛用品などを並べます。みなさんに思い出話をたくさん語っていただける場にしたいと思います。
※当日は平服にてお越し下さい。
※香典、供花につきましてはご辞退申し上げます。
お問い合わせ(ヒューマンケア協会)
電話: 042-646-4877 メール:humancare@nifty.com
主催: NPO法人 ヒューマンケア協会
共催 : 自立生活センター日野・ILみなみTama
全国自立生活センター協議会・DPI日本会議
【訃報】JIL創設者の中西正司さんがご逝去されました
全国自立生活センター協議会(JIL)
中西さんらがJILを立ち上げ、強靭なリーダーシップで、
改めて最後の最後まで障害者運動家であり続けた中西さんのこれま
どうか、先に旅立たれた日本中いや世界中の障害者運動の諸先輩、
今まで本当にお疲れ様でした。
2025年4月11日
NPO法人全国自立生活センター協議会
理事長 平下耕三

写真1:2016年にNCIL事務局長(当時)のケリー・バックランドさんを迎えての講演会にて、挨拶をする中西さん。横断幕には「公益財団法人 キリン福祉財団助成事業 アメリカ自立生活IL運動の現在」と書かれ、NCIL、キリン福祉財団、JILのロゴマークが並ぶ。中央で挨拶する中西さんと、マイクを持つ介助者。後ろには手話通訳者が写っている。

写真2:2018年に来日した、NCIL代表(当時)のブルース・ダーリングさん、同副代表(当時)のサラ・ラウンダーヴィルさんを、中西さんのご自宅でお迎えしたときの一枚。左から、中西由起子さん、ブルースさん、サラさん、中西さんが、それぞれ笑顔で写っている。

写真3:2016年に在日本米国大使館にて、ADA法の制定に深くかかわったトム・ハーキン元上院議員を迎えてのレセプションに出席された際の一枚。前列左から、中西正司さん、中西由起子さん、後列左から、トム・ハーキン上院議員、キャロライン・ケネディ大使(当時)が笑顔で写っている。
2024年度オンラインシンポジウム〈知的障害者の自立生活 これまでとこれから〉
知的障害者の自立生活に関するオンラインシンポジウム開催のお知らせ
知的障害のある人の自立生活を考える会主催による2024年度オンラインシンポジウム「知的障害者の自立生活 これまでとこれから」が開催されます。本シンポジウムは、知的障害のある人が他の人々と同様に、自分の住む場所や共に生活する人を自由に選択できる社会の実現を目指して開催されます。
当会は2017年より、知的障害のある人の地域での自立生活を支援するため、全国各地の実践事例の共有や関係者のネットワークづくりに取り組んできました。
開催概要
日時:2025年3月1日(土)13:00-16:30(予定)
形式:オンラインウェビナー
参加費:カンパ制
情報保障:パソコン文字通訳(パソコン文字通訳者会ユビキタス)
手話通訳(ミライロ)※Zoomの手話ビュー使用予定
プログラム内容
第一部:「重度訪問介護の対象拡大から10年——これまでを振り返る」
2014年から開始された重度訪問介護の重度知的障害者への対象拡大について振り返ります。この10年間で利用者数は4倍(316人から1250人)に増加し、多くの方々が自分らしい生活を実現してきました。DPI日本会議副議長の尾上浩二氏をお招きし、制度改革の経緯や今後の展望についてお話しいただきます。
第二部:「自立生活の運動はいまどこに? 支援のコーディネーターが語り合う」
知的障害のある人の自立生活を支えるコーディネーターたちが、現場での実践や課題について意見を交換します。制度化されていない支援の調整役として、どのような役割を担い、どのような課題に直面しているのか、今後の展望も含めて議論します。
登壇者プロフィール
・尾上浩二氏(DPI日本会議副議長)
1960年大阪生まれ。46年にわたる障害者運動の経験を持ち、バリアフリーや介護保障の分野で活躍。現在は内閣府障害者施策アドバイザーも務める。
・岡部耕典氏(早稲田大学)
福祉社会学・障害学が専門。重度訪問介護を利用する知的障害のある息子を持つ立場から、障害者福祉政策の研究と提言を行う。
・田中恵美子氏(東京家政大学)
障害者の自立生活、結婚・子育てなど、地域での暮らしに関する研究者。NPO法人での支援経験も持つ。
グループ視聴について
本シンポジウムは、グループでの視聴を推奨しています。職場や地域の仲間と一緒に視聴し、意見交換を行うことで、より深い学びの機会となることが期待されます。特に、オンライン参加に不慣れな方々のサポートとして、グループでの参加をご検討ください。
後援:
全国手をつなぐ育成会連合会
NPO法人東京都自閉症協会
NPO法人全国自立生活センター協議会
NPO法人DPI日本会議
NPO法人自立生活センター小平
全国障害者介護保障協議会
昭和音楽大学
※お申し込みやその他詳細については、主催団体までお問い合わせください。
詳細情報・申し込み方法
詳しい情報は主催団体のホームページをご覧ください。
https://jirituseikatu.jimdofree.com/2025.03.01/
お申し込みは以下のURLから受け付けています。
https://everevo.com/event/89436
広報用 シンポジュウムチラシ
社会福祉法人グロー 北岡賢剛前理事長の判決
についてのJILとしての声明文
についてのJILとしての声明文
2024年12月23日
社会福祉法人グロー 北岡賢剛前理事長の判決
についてのJILとしての声明文
特定非営利活動法人 全国自立生活センター協議会
代表 平下耕三
私たちは、どんな重度な障害があっても地域で当たり前に生活し、障害者権利条約の完全実施に向けて障害のある人とない人が分け隔てられることなく、誰もが差別されず、共に生きられる社会(インクルーシブな社会)を目指して活動する障害当事者団体です。全国110か所を超える障害当事者団体(自立生活センター)で構成しています。
私たち全国自立生活センター協議会(以下JIL)は、2024年10月24日に東京地方裁判所で判決が下された社会福祉法人グローの北岡賢剛前理事長による性加害・ハラスメント行為について、北岡氏が関与する組織と連名で、政府等に対して共同要望を出すなどの行動を共にしてきた団体として、私たちは強い怒りと失望ともに、自身の責任も深く痛感しています。
まず北岡氏に対しては本判決を受け、被害女性と真摯に向き合い、被害女性への謝罪と賠償を速やかに行うことを求めます。
他方、被害者への賠償額が被害の深刻さに比して不十分であることにも、私たちは失望せざるを得ません。
この賠償額が、性加害や差別行為の深刻さを過小評価している現状は、日本社会の問題として解決が求められるべきです。
本件は重大な人権侵害です。障害者の福祉に携わる者が、権力を乱用して職員にハラスメントを行ったことは、決して許されるものではありません。本来であれば、裁判が起きたときに、JILとしても内部でもどう行動するか話し合われるべきでした。この点は人権擁護団体として不十分な対応であったと深く反省するとともに、その責任を真摯に受け止めます。また、判決が出された後もJILとしての声明文の公表までに相当の時間を要してしまったことは、多数の理事による合議体である組織構造上の問題でもあり、本件を教訓に今後の組織運営のあり方について十分に検討して改善していく所存です。
被害女性が提訴し、裁判が進められる中、JILとしては判決が出るまで意見表明を控えてきましたが、私たちは障害がある人もない人も人権が尊重される社会を目指し、反省をもとにした具体的な行動を進めていかなければなりません。 被害者の方々の苦しみを真摯に受け止め、再発防止が徹底されるために、声を上げ続けていくとともに、問題を長期間放置してきた姿勢を深く反省し、迅速かつ積極的に対応する体制の整備を進めます。
また、北岡氏が大きな影響力を持ち、社会福祉法人グローが事務局となり長年運営されてきたアメニティーフォーラムについて、自己反省の意味でも今年度JILとしての参加は見送り、来年度以降については十分な議論を重ね検討を行ってまいります。
今後、同様の事態を繰り返さないために以下を実施いたします。
1.対応の振り返り内部体制の強化
過去の対応を振り返り、人権侵害の早期発見と防止に向けた内部体制を強化します。
2.啓発活動の充実
性暴力やハラスメントの防止に関する委員会設置や研修を推進し、福祉現場における安全と平等の意識を高めます。
3.被害者支援の充実
被害者の声を尊重し、支援体制の整備と改善に努めます。また、声を上げやすい環境づくりを推進します。
社会福祉法人グロー 北岡賢剛前理事長の判決
についてのJILとしての声明文
国立病院機構鈴鹿病院における虐待事案
に対する抗議文
に対する抗議文
2024年7月25日
国立病院機構鈴鹿病院 病院長 殿
三重県知事 殿
全国自立生活センター協議会
代表 平下 耕三
国立病院機構鈴鹿病院における虐待事案に対する抗議文
私たち、全国自立生活センター協議会は、どんな重度な障害があっても地域で当たり前に生活し、障害のない人と同じ権利を持ち、地域の中で共に生きる社会の実現を目指して活動をする障害当事者団体です。全国100ヶ所を超える障害当事者団体(自立生活センター)で構成しています。
この度、鈴鹿病院における医師や看護師による入院患者に対する虐待行為が確認されたとの報道を受け、深い憤りと強い衝撃を感じております。
報道によれば、鈴鹿病院では昨年、医師や看護師ら8人が障害のある患者に対して「ごみ」「ダンゴムシみたい」などの暴言を吐くといった虐待行為が合計36件確認されたとのことです。また、入浴後の患者をバスタオルだけで15分間放置するなどの人間の尊厳を無視した不適切な対応が行われたことが明らかになりました。これらの行為は、患者の尊厳を著しく損なうものであり、絶対に許されるべきではありません。
さらに、貴院がこれらの事案を把握していながら、自治体への通報を怠っていたことは、障害者虐待防止法に明確に違反しており、極めて遺憾です。このような対応は、障害者やその家族の信頼を完全に失うばかりでなく、貴院の信頼性にも深刻な損害を与えるものです。
私たちは以下の点について、強く抗議し、直ちに改善を求めます。
≪当事者への謝罪≫
●直接の被害を受けた患者およびその家族に対して、貴院の最高責任者から正式かつ誠実な謝罪を行うこと。
≪再発防止策の徹底≫
●今後同様の事態が発生しないよう、職員に対する徹底した教育・指導を行うこと。
●定期的な内部監査および外部からの厳格な監査を実施し、その結果を公表すること。
≪透明性の確保≫
●今回の事案に関する本人・家族等への聞き取り等、詳細な調査報告を行い、その結果を全ての関係者やマスメディアに公開すること。
≪自治体との連携強化≫
●障害者虐待防止法に基づく義務を果たし、自治体への迅速な通報および連携を強化すること。
≪虐待防止に関する研修の徹底≫
●二度と虐待を起こさないために人権意識を高めるための研修を必ず行うこと。 (なお、私たち全国自立生活センター協議会は、障害のある当事者による虐待防止 ワークショップを実施していますので、研修に協力することが可能です)
≪社会的入院の精査と地域移行の仕組みづくり≫
●現行の障害者施策においても施設や病院からの地域移行が推奨されており、貴院における社会的入院の精査と地域移行の仕組みづくりを早急に行い、地域の相談支援事業所等、関係機関と連携協力し、患者の地域移行に取り組むこと。
これらに関して検討をし、結果を報告すると共に経緯、謝罪、再発防止対策をWEBサイトにおいて公表することをお願い致します。
また、三重県に対しても、以下の点について強く要望いたします。
≪監視体制の強化≫
●障害者福祉施設や医療機関に対する定期的かつ厳格な監査を実施し、虐待行為が発生しないよう予防策を講じること。
≪通報制度の周知徹底≫
●障害者虐待防止法に基づく通報制度を医療機関や福祉施設に徹底的に周知し、早期発見・早期対応が行える体制を整えること。
支援体制の充実
●虐待被害者およびその家族に対する支援体制を強化し、必要なサポートを迅速かつ適切に提供すること。
私たちは、障害者が安心して医療を受けられる環境の整備を求め、貴院および三重県が今回の問題を真摯に受け止め、迅速かつ具体的な対応を取ることを強く望みます。
以上
国立病院機構鈴鹿病院における虐待事案に対する抗議文
旧優生保護法国家賠償の最高裁判決
に関する声明
に関する声明
2024年7月12日
旧優生保護法国家賠償の最高裁判決に関する声明
全国自立生活センター協議会
代表 平下耕三
私たち、全国自立生活センター協議会は、どんな重度な障害があっても地域で当たり前に生活し、障害のない人と同じ権利を持ち、地域の中で共に生きる社会の実現を目指して活動をする障害当事者団体です。全国100ヶ所を超える障害当事者団体(自立生活センター)で構成しています。
7月3日、旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めている裁判のうち、仙台や東京などで起こされた5つの裁判の判決が最高裁判所大法廷で言い渡されました。
戸倉三郎裁判長は、「旧優生保護法の立法目的は、当時の社会状況を考えても正当とは言えない、生殖能力の喪失という重大な犠牲を求めるもので、個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反し、憲法第13条に違反する」と指摘しました。また、障害のある者などに対する取り扱いで、法の下の平等を定めた憲法第14条にも違反するとして、旧優生保護法は憲法違反だとする初めての判断を示しました。そのうえで原告側の訴えを認め、5件のうち4件で国に賠償を命じる判決が確定しました。
不法行為から20年が過ぎると賠償を求める権利がなくなる「除斥期間」については、「この裁判で請求権が消滅したとして国が賠償責任を免れることは、著しく正義・公平の理念に反し容認できない」として認めませんでした。今回の最高裁での判決を私たちは支持します。
他方、1996(平成8)年まで48年間続いた旧優生保護法は、障害を理由とした不妊手術を認め、手術を受けた人は全国でおよそ1万5000人に上るとされています。
不良な子孫を残さないという目的で生殖能力を失わせ、自己決定権を奪ったことは、国家として障害のある私たちの存在を否定した極めて重大な人権侵害です。法改正後も国会で適切かつ速やかな補償の措置を講じることが強く期待されたにも関わらず、一時金320万円の支給にとどまり、国は不誠実な対応に終始しました。
今後は、国として明確な謝罪を求めます。また、手術を受けた人は全国で2万5000人に及んでいます。現在では、一時金を申請した一部の人にしか支給されていません。今後、立法での解決が求められますが、多くの被害者が声をあげられる仕組みを構築し、すべての被害者が救済され、適切な支援が受けられることを強く求めます。再発防止の取り組みとしては、優生保護法の歴史とその影響を正しく理解し、広く社会に共有するための教育と啓発活動を行い、すべての人々の人権を最大限尊重する法制度を構築し、差別や不当な扱いを排除するための見直しを行うことを求めます。
そして、政府のみではなく、マスメディアなどを含め、すべての人々が尊厳を持って生活できる社会の実現に向けた取り組みを、私たちと共により加速させていくことを求めます。
以上
旧優生保護法国家賠償の最高裁判決に関する声明
精神保健福祉法附則決議に基づく身体拘束
についての要望
についての要望
私たち全国自立生活センター協議会は、5月13日に厚生労働省に以下の要望書を提出しました。
厚生労働大臣
武見 敬三 殿
2024年5月10日
全国自立生活センター協議会
東京都八王子市明神町4-11-11シルクヒルズ大塚1F
代表 平下耕三
精神障害プロジェクト一同
「精神保健福祉法附則決議に基づく身体拘束についての要望」
私たちは全国120か所にある、障害者の権利擁護と地域での自立生活を実現する「自立生活センター」の集まりです。私たちは障害の種別を問わず、人として尊厳をもって地域で自立生活することをサポートし、地域社会の変革に取り組んでいます。
2022年11月の第210回国会にて精神保健福祉法の改正がされ、身体拘束に関しては衆議院附帯決議で、「隔離・身体的拘束に関する切迫性、非代替性、一時性の要件を明確にするため、関係団体との意見交換の場を設け、厚生労働大臣告示改正を速やかに進めること」と決議され、参議院附帯決議では「隔離・身体拘束の対象が実質的にも限定されるよう必要な措置を講ずること」と決まりました。
現行の精神保健福祉法では身体拘束を許可する要件として「不穏・多動の顕著な場合」とあり、判断基準がとても曖昧で、医師の裁量権がとても大きく、病院間、地域間、医師の資質の差が激しい精神科病院において、患者は常に身体拘束の脅威にさらされ、人権侵害の危機がある状態です。この法律がある限り、患者が「拘束しないでくれ」と主張しても、「不穏・多動がある」と医師が判断すれば法律に基づき隔離、身体拘束が行われます。2024年2月には兵庫県神戸市の精神科病院で7日間の身体拘束後に患者が死亡する事件で遺族が病院を相手どり訴訟を起こしました。保護室の監視カメラには「不穏・多動」の様子は見られないと遺族は主張しています。このように私たち精神障害者の人権・生命・自由が全く軽く扱われてしまいます。
私たち精神障害者はこの法律のために、長い間、不当な身体拘束・隔離に苦しめられてきました。自立生活センターに関わる精神障害当事者も「保護室に隔離された時に医師の診察がなく看護師の判断で隔離された」「保護室から出してほしいと訴えても取り合ってもらえないこともあった」などの声があります。
また近年ではこうした違法性のある身体拘束について各地で裁判も行われています。身体拘束は人としての尊厳を大きく傷つけ自由を奪い、その結果、自己肯定感が大きく傷つけられ、気力を奪われ、長期入院につながることや、退院後も自己の尊厳を取り戻すことに多くの時間がかかり、場合によっては精神科病院への不信感、自殺念慮や再入院につながることもあります。また身体的にも肺塞栓症などを起こし死に至るケースや身体的損傷を受けることがあります。
いうまでもなく病院は本来患者を治療、守る機関であり、法律により病院が人権侵害を行う権限を強く持っていることは決して許されてはならないことです。安易な身体拘束は、病院側の治療体制、看護体制を患者に押し付けるものであり、これは国連の障害者権利委員会による総括所見に真っ向から反する状態です。
また身体拘束をしない治療を進める病院が国内、国外でも存在し、こうした実例が身体拘束によらない治療が非現実的でないことを証明しています。以上のことにより、厚生労働大臣に以下のことを切に要望いたします。
1 2021年10月に名古屋高裁で、2016年に石川県の精神科病院「ときわ病院」での身体拘束で患者が死に至った事件で、このケースの身体拘束が違法であるという判決が出ています。これは「ときわ病院」が特殊なわけではなく、精神科病棟では日常的にある身体拘束の典型的な事例といえます。このように現行の法律では、安易な身体拘束が、患者本人の意向を無視して行われます。国連の障害者権利委員会の総括所見を踏まえ、身体拘束を原則としてなくすために、「身体拘束は原則としてなくすこと」「身体拘束に代わる患者を守る安全な治療法を確立するために、個々の病院で身体拘束ゼロに向けた計画と、海外などの事例研究(オープンダイアローグ等)や研修を行い身体拘束ゼロを現実的実現に向けた具体的な方策を必ず作り実現すること」と厚労省通達を出すこと。
2 告示改正にあたっては障害者団体など当事者団体との意見交換の場を必ず持ち、真に患者の生命、人権を守るための法律とすること。
3 身体拘束は基本的に行なってはならないと告示改正に入れること
理由としては身体拘束は人権を奪う行為で、その多くは医療側の体制不備によるものであり本来あってはならない。また身体拘束を行うことによって、医師・看護師などと患者との信頼関係を壊しその後の治療に大きな影響を与えるものである。患者にとって尊厳を傷つけられることでトラウマや過剰なストレスを生むなど入院時のみならずその後の日常生活に大きな影響を与えるものである。また身体拘束は、医師・看護師など医療側の権力を増大させ、患者との間に意識的・無意識的に支配服従関係を強制的に与えるものである。このことが医療者から患者への虐待へとつながっていく一つの要因となっている。従って基本的に身体拘束は行ってはならない。
4 3が基本的な大きな方針であるが、現状の医療体制では患者の生命、重大な身体的な危険が及ぶ場合で他の代替案がなくやむをえず身体拘束をする場合は、ごく短時間だけ行うようにすること。また「不穏多動」の文言は病院の人員など体制を補うために安易に当てはめることができるので、この文言は廃止すること。
5 やむをえず身体拘束をする場合は「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要件をすべて満たすこと、また3要件のうち1つでも要件から外れた場合は速やかに身体拘束を解除すること。
6 身体拘束によらず「代替性」を考える場合、従来の医療よりも柔軟に対応し、当該患者の意思を聞き取るために障害当事者アドボケーター(権利擁護者)によるピアカウンセリングの手法を使った聞き取りや病院訪問を積極的に受け入れること。法学的知識、人権に基づく客観的な判断を行うために弁護士を積極的に受け入れること。通常時よりこれら他職種との連携をとり、急性期での隔離・拘束に変わる代替策を確立すること。
7 上記要件を全て満たし、やむをえず身体拘束等をする場合には本人にわかりやすい十分な説明をし理解を得るとともに、当該患者の話を傾聴し最大限主体的に行える治療環境を整備すること。本人が興奮状態などで十分な説明ができない場合もできる限り丁寧に治療方針を説明し、当該患者の状態が収まり次第、再度担当医から速やかにわかりやすく説明すること。
8 医師を含む医療に関わる全ての職員に対し、身体拘束廃止に向けての研修を年1回以上定期的に行い、人権研修と隔離・拘束に代わる治療を研究・研修し、早急に実施に移すこと。
9 「精神保健福祉法第 21 条第 4 項の厚生労働省令で定める精神科病院の基準」に規定されている通り、行動制限最小化委員会が身体拘束を行う病院で必ず設置され、機能していることを確認するために都道府県は随時調査をすること。特に身体拘束事例の多い病院に対しては状況に応じ3ヶ月に1回など調査を厳正に行うこと。また精神医療のみならず、人権擁護の観点からも、弁護士、人権擁護団体、障害当事者団体の視察を受け入れ制限されることのないように、厚生労働省から告示すること。
10 以上を満たすために、都道府県各自治体は抜き打ちで各精神科病院に実地調査を行うことがあることを明記すること。
以上の項目について、2024年7月30日までに回答を頂けるようお願い致します。
精神保健福祉法附則決議に基づく身体拘束についての要望
国立病院機構「大牟田病院」における性的虐待事案
に関する抗議声明
に関する抗議声明
2024年5月10日
国立病院機構「大牟田病院」における性的虐待事案に関する抗議声明
全国自立生活センター協議会
代表 平下 耕三
私たち、全国自立生活センター協議会(以下「本会」という。)は、どんな重度な障害があっても地域で当たり前に生活し、障害のない人と同じ権利を持ち、地域の中で共にある社会の実現を目指して活動する障害当事者団体です。全国110ケ所を越える障害当事者団体(自立生活センター)で構成しています。
本会内部組織である人権委員会では、各地の自立生活センターと連携し、障害のある者一人ひとりの権利を守るための取り組みを通し、制度や社会の変革を通じて権利擁護活動、虐待防止ワークショップ等の普及活動。同じく本会内部組織である脱施設プロジェクトでは、入所施設等の閉鎖を目指し、自立生活支援を強化し、障害者の地域生活を実現するために、権利条約19条の履行やSDGsの目標達成に向けた取り組みです。
福岡県大牟田市にある国立病院機構「大牟田病院」における性的虐待事案に対する一連の報道について、次の通り声明を発表します。
5月1日の報道によれば、看護師、介護士あわせて 5 人の男性職員が身体に障害のある男女11名に対して、陰部を揉んだり、胸付近を触ったりする性暴力をしていたという驚愕の事案が明らかになりました。5 月 2 日に行われた病院の記者会見では、「特定されるため」等という理由で、ほとんどの情報が開示されず、大変曖昧なものでした。
私たちは障害がある者として、被害者の言葉にならない恐怖、痛み、辛苦、恥辱を思うと、心が押しつぶされる思いです。そして勇気をもってこのような事案を公にしてくださった方に深い畏敬の念を抱きます。
取り急ぎ、現在の被害者の安全が十分に確保されるために必要な対応を速やかに行ってください。ただ加害者との接触を断つだけでなく、被害者が安心を得られるよう、心身共に配慮したケアや介助を提供してください。特に女性被害者にとっては、望まない異性介助がフラッシュバックなど二次被害を生じさせる可能性も考えられます。被害者の意向を大切にし、本人の安心できる介助体制を整えてください。
また、傷ついているのは直接被害を受けた患者だけではありません。周囲の患者もショックや不安の中にいることと、他の被害者がうもれている可能性を想定し、患者全員が今日を安心して生活できるよう、迅速な対応をお願いします。
今回の虐待行為は、2022 年 9 月に国連障害者権利委員会から出された「総括所見」「脱施設化ガイドライン」にあるように、障害のある者を施設、療養病院、精神科病院等、特定の生活様式に隔離することで生じる弊害であると言わざるを得ません。また、異性による介助が慢性化している事も性暴力の原因となります。
脱施設プロジェクトで、力を入れてきた取り組みの1つ、筋ジス病棟の地域移行では、未だに病院内での地域移行の妨害行為、患者の人権を踏みにじる対応が散見されています。今回の報道も、そういった取り組みの成果であると確信しています。
また、こういった一連の事案から必要最低限の看護や介護となり、質の低下や何より患者の人権を否定した対応にならないか懸念しています。
本来、本件は犯罪としても取り扱われるべきであり、事件として障害のない人に対する取り扱いと同様の対処をするべきです。こういった点においても病院当局の「甘さ」がみられます。
国立病院機構「大牟田病院」に対し、今回の性的虐待事案に深い憤りと懸念を表明し、被害者の尊厳を守り、再発防止に全力を尽くすことを求め、下記の通り厳重に抗議します。
記
<大牟田病院>
1.大牟田病院は、事実の公表および処分の徹底を行ってください。
2.被害者の受けた大きな心身の傷のケアを丁寧に行うため、適切な意思決定支援を行い、ピアサポーターと共に最大限の支援を行ってください。
3.二度と虐待を起こさないために人権意識を高めるための研修を必ず行うこと。 (なお、
私たち全国自立生活センター協議会は、障害のある当事者による虐待防止 ワークショ
ップを実施していますので、研修に協力することが可能です)
<福岡県および大牟田市>
1.福岡県および大牟田市は、検察庁、警察とも連携し、事実の解明と然るべき措置を行ってください。
2.指定権者として責任をもち、早急に全国の療養型病院の入院患者に同様の被害がない
か、第三者委員会を設置し、調査を行ってください。
3.仮に重大な問題が発覚したら包み隠さず公表してください。
<厚生労働省>
1.現行の障害者虐待防止法の最大の問題点は、今回の様な病院、そして学校や保育所等について、未だに発見者の行政等への通報義務を対象外としていることです。早期に見直しを行い、被害者が真に守られる法改正を行ってください。
2.これまでの収容型障害福祉のあり方を早急に見直すため、速やかに検討会を立ち上げてください。
以上
滝山病院の看護師による患者暴行事件に関しての抗議及び要望