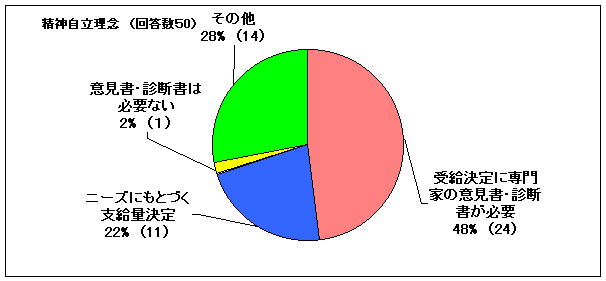6.精神障害者のサービス利用について |
(1)ホームヘルプサービスにいたらない方への取り組み(自治体)
|
自治体の精神障害者向けサービス実施状況について、ホームヘルプサービスの利用にいたらない方に対する独自の取り組みを行っているという回答は約4割にとどまる。 |
| 自治体の取り組み内容 |
・共同住宅運営事業・手帳のある方に交通カードの支給・24時間緊急医療相談(医師会と市が協力して行っている)ホームヘルプサービスは、症状が安定していて、単身の方にしか派遣できないのが現在の状況。そのため市では60~70%の人はホームヘルプサービスを利用できていないので、その穴埋めとして上記のような体制をとっている。 |
| ・ボランティア活動等では行なっている |
|
| ・当事者が主体になって行う自立生活センター的なものはなく、行政が軸になり市内に2ヶ所の生活支援センター・3ヶ所のデイサービス・1ヶ所のグループホームがある。 |
|
| ・講座開催「精神保健福祉学習会」 |
|
| ・①個別支援として、施設利用や就労等社会復帰に関する相談を随時②集団支援として、毎週金曜日、市の保健所で、精神障害の方のグループ活動。また月1回精神障害者の方と一緒に生活されている家族を対象に家族教室。<市(保健所)が行っていること/聞き取りで得た回答> |
|
| ・精神障害者通院医療費補助(国の制度による補助で残る自己負担分5%を助成)・重度障害者福祉タクシー利用助成か障害者公共交通機関利用助成のいずれかを選択(精神障害者保健福祉手帳1級が対象) |
|
| ・本人の病状安定がホームヘルプサービスを利用できるかどうかの判断材料になっており必要な人にサービスが出せない状態であるが行政の保護士や医療スタッフが補完している状況 |
|
| ・作業所、社会復帰施設に通う際の交通費を一部支給するもの。6ヶ月以上居住している在宅の人が対象。金額は、月額で通所実日数に運賃を乗じた額の1/2で上限1,000円。 |
|
| ・精神障害者が理事に入っているNPOが、生活支援を行っている(代表は健常者、元行政職員夫婦)。障害者生活支援事業の中にも同NPOが関わり精神障害関係の相談対応を行っている。 |
|
| ・保健士やケースワーカーが随時、電話での相談や必要時、訪問を行い、相談やサービス紹介を行っている。 |
|
(2)ホームヘルプサービス利用について |
ホームヘルプサービス利用について、2割の団体はニーズにもとづく支給量決定が行われると回答しているものの、半数が古い理念のまま(サービスを使わなくなることが自立である)のサービス提供がされており、上限が設定されていたり医師などの専門家からの意見書や診断書等の提出が必要と回答している。 |
| 市保健所の精神福祉士がケアマネ資格を取り、サービスを決めたり、また、決定までにたいへん時間がかかる場合や、診断書は必要がなくとも実質はサービスを受けられない状況だという回答があがっている。 |
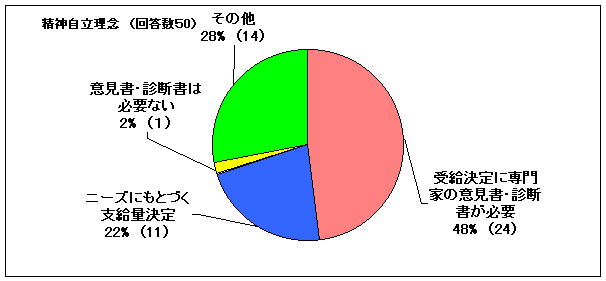 |
(3)ホームヘルプサービス利用による自立 |
CILのある市区町村で精神障害者でホームヘルプサービスをつかいながら自立をしている人がいるという回答は54%にとどまるが、当事者にとって適切な支援があれば自立が可能であるという。 |
| 自立に必要な支援 |
・支援費制度の確立 |
| ・精神面のサポート |
| ・本人が興味をもってできる日中活動の場。仲間作りを広げる関係作り。 |
| ・単に介助だけではなく、相談体制も充実させる。 |
| ・家事の代行にとどまらず、本人自身が生活を営みやすい形への促し、環境整備を目標とした支援。 |
| ・必要なときにヘルパーが派遣されるシステム・住宅確保・所得保障・就業支援等 |
| ・食事と衛生面の管理 |
| ・精神障害の相談窓口を地域に設置する。・行政・当事者等へのヘルプの認知度をあげる |
| ・当事者を主体として組織がホームヘルプ事業。現在実施している一般事業者の主任が精神障害者を「怖い」と公の場でも言うほどレベルが低いため、支援とはいえない程度の仕事しかしていないと思う。 |
| ・地域の人々や家族の理解。行政とのホームヘルプサービスについての粘り強い交渉。 |
(4)自立支援を行う上で必要な情報、体制等 |
・ピアカウンセリング、自立生活プログラム |
| ・①障害当事者の講師による「本当に望む支援」に関する研修会 ②各センターの取り組みを検討しあう交流会 ③理解促進のための市民参加型のイベント |
| ・地域で暮らすことに理解のある医師および病院の情報・実際に自立している方の事例および情報(トラブルが起きたときにどう対応しているか、トラブルの事例) |
| ・CILで精神障害者の方と関わっていくためのリーダー研修。 |
| ・ホームヘルプをコーディネートする上での研修。 |
| ・当事者主体を強化したヘルパー研修が行えるような講習会。 |
| ・他市町村のホームヘルプ実施状況・ホームヘルプ事業所に対する研修と市町村に対するホームヘルプの研修 |
| ・医療的協力体制 |
| ・神経症性障害、人格障害等の利用者が見込まれる中、研修等では統合失調症、気分障害が中心であるので、それらの基礎研修が必要。 |
| ・①実際に対応しているヘルパーがどんなことで困っているか、他機関・医療機関などの支援を必要としているか知りたい。②精神障害者にも高齢のほうが増えているので、高齢者のサービスへの知識が支援する側にも必要。③就労支援関係のサービス、最近新しく打ち出されているが、具体的にどのように利用できるのかが把握しにくい。 |
| ・長く社会生活を続けるのなら、病識を身につけるトレーニング、通院、服薬を守る。本人のニーズにより少しずつ病識を持てるように働きかける。制度、福祉サービス等相談受諾、勉強会など。 |
| ・精神障害者を持つ家族の会等のネットワーク作り・相談窓口・作業所等の開放・地域の人たちとのふれあい活動・市町村の担当者と家族の会との情報交換会 |
| ・まずグループホームの作り方を知りたい |
| ページトップへ戻る |
JIL年鑑トップへ戻る |