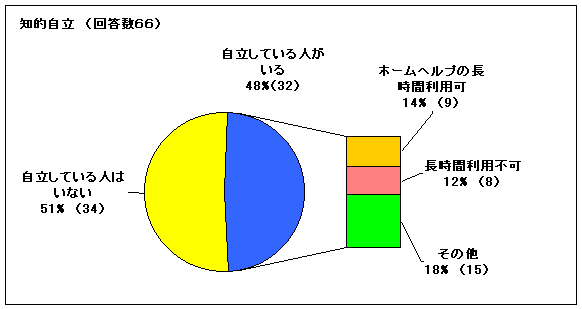5.知的障害者のサービス利用について |
(1)支援費制度の利用にいたらない方への取り組み(市区町村・CIL)
|
支援費制度の利用にいたらない知的障害の方について、市区町村やCILで独自の取り組みをおこなっていると48%のセンターが回答している。 |
| 市区町村の取り組み内容 |
・障害児(者)地域療育等支援事業委託 |
| ・地域福祉推進事業・心身障害者(児)通所授産補助事業 |
| ・生活アシスタント事業 |
| ・青年学級、スポーツ大会 |
| ・知的障害の当事者団体による人権セミナー、学集会・交流会・市の単独事業で放課後の居場所づくり、交流の場づくりなど。 |
| ・知的障害の事業所もかなりあり、制度にいたらない状況であっても、作業所やボランティア団体を中心にサポートを行っている。 |
| CILの取り組み内容 |
・支援費以外の介助派遣 |
| ・自立生活プログラムなどを通して、介助者との付き合い方などを学ぶ機会を設けている。 |
| ・地域移行へ向け、以下の取り組みを行っている。外出、レクリエーション(カラオケ、ボーリング、映画鑑賞、買い物、散歩、遊園地、登山、プール等)・宿泊体験(調理、掃除、洗濯、その他自立生活に必要なこと) |
| ・自立体験室の利用、部屋探し、金銭管理、就労支援などを行っている。16年9月より、マンションを2部屋借りて、支援費のグループホームを開設。 |
| ・当事者によるイベント企画、しゃべり場(交流会)、勉強会、ピープルファースト大会への参加、自立生活体験室の充実、当事者により作成される機関誌発行、ピアカウンセリング講座 |
| ・CILの季節行事に参加してもらったり、CIL関係者の自宅に来てもらったりして交流をしている。 |
| ・ピープルファーストジャパンに入会し、県内で準備会等を開いている。 |
| ・①生活情報・福祉制度情報の提供、利用支援 ②体調不良時の医療機関への付き添い③余暇活動の提案 |
| ・社会参加支援ガイドヘルパー制度(無資格者でも自薦登録により活動できるガイドヘルプ制度) |
| ・知的障がい者のためのガイドヘルプ養成 |
| ・生活ホーム・グループホーム・地域交流会・サマーホリデープログラム |
| ・知的障がいを持つ人の支援研修として①知的障がいについて②その支援について③支援費制度に絡めた事業所としての支援研修を行っている。 |
(2)ホームヘルプサービス利用による自立状況
|
CILのある市区町村に知的障害者でホームヘルプサービスを使いながら自立している人がいると約半数が回答している。自立生活をしている知的障害者のうち、身体障害者と同じように長時間のホームヘルプが認められていると回答したセンターは3割で、認められていないと回答したセンター数も同じ割合である。 |
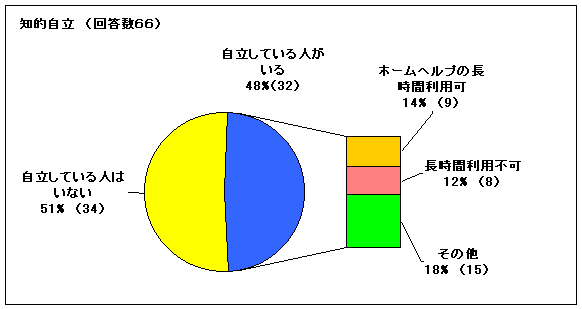 |
(3)自立支援を行う上で必要な情報や希望する研修
|
・実際に自立している方の経緯などの詳しい事例。 |
| ・ヘルパーと知的障碍者の接し方。・病状や症状にたいしての理解、及び接し方の研修。 |
|
| ・ピアカウンセリング、自立生活プログラムの仕方 |
|
| ・①障害当事者の講師による「本当に望む支援」に関する研修会 ②各センターの取り組みを検討しあう交流会 ③理解促進のための市民参加型のイベント |
|
| ・〔①自閉症についての知識、接し方、気をつけなければいけないこと②知的障害についての正しい理解、制度上の説明会③自閉症と知的障害の違い〕をヘルパーさんがわかるような研修 |
|
| ・重度といわれる障害のある人たちへの自立支援 |
|
| ・地域権利擁護事業について。成人後見人制度についてのhow to 研修・講習会など。 |
|
| ・親の意識変革をどう行っていけばよいのか。 |
|
| ・知的障害者が地域で暮らす支援の経過措置としてグループホーム設立に向け、運営にあたっての具体的な方法やよい点、問題点等細やかな情報交換を行えるような研修、又、行うにあたっての検討会議の中でCILの理念がどこまで反映できているか等の経過。 |
|
| ・グループホーム、作業所、更生施設、家族など複数の支援機関との連帯をどのように調整して支援していけばいいのか、他の団体ではどうしているのか情報が欲しい。 |
|
| ・当事者団体発足のあしがかり。自立支援のための留意点。当事者スタッフの育成 |
|
| ・当事者間の組織作りとその運営を通した、いわゆるピープルファースト活動を地域において育成するのが望ましい。 |
|
ページトップへ戻る |
JIL年鑑トップへ戻る |