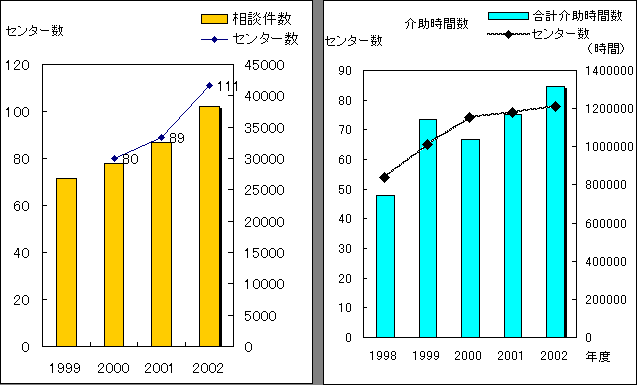
|
障害種別 |
利用者人数(人) |
|
身体障害 |
2915 |
|
視覚障害 |
103 |
|
知的障害 |
809 |
|
精神障害 |
33 |
|
その他 |
100 |
|
合計 |
3960 |
2.サービス別まとめ
(1)相談・情報提供事業
加盟センター数の増加に伴い、自立生活センターの基本事業でもある相談件数は、年々増加し、2002年度実績では、合計38266件の相談がよせられた。相談内容については、自立に関することや住宅改造、制度などに関する情報提供、また介助時間の不足や介助者との関係作り、交通アクセスに関することなど多種に渡っている。また相談から権利擁護活動につながるケースも少なくない。
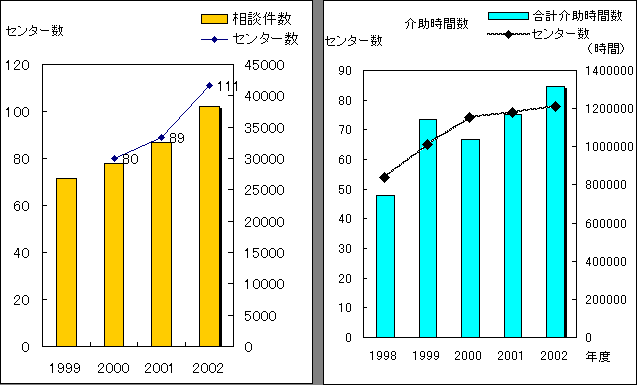
(2)介助派遣サービス
2003年度よりスタートした支援費制度に先駆けて各団体でヘルパー事業を受託する団体が増加したこともあり、2002年度介助派遣時間実績では2001年度実績と比較とし12%増となっている。また障害種別の派遣時間数もそれぞれ増加しており、視覚障害者について3.6倍、知的障害者で1.6倍の増加となっている。JILの支援費事業量調査においては(2003年4月調査)、全国のホームヘルプ事業費の10.6%と、自立生活センターが全体の1割以上を占めており、支援費制度が開始された2003年度については、さらに増加が見込まれている。
・介助サービス派遣時間数(障害種別) 単位:(時間)
|
身体 |
視覚 |
知的 |
精神 |
その他 |
|
|
2002年度 |
1,215,685 |
8,967 |
74,339 |
2,158 |
16,767 |
|
2001年度 |
1,055,790 |
2,433 |
46,032 |
1,541 |
21,679 |
・介助サービスの利用者割合
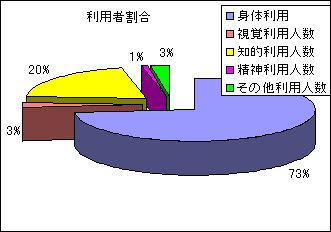
・介助サービスにおける各種対応状況
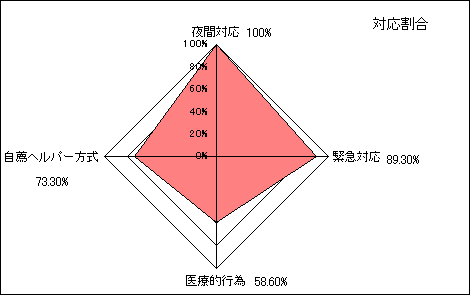
自立生活センターと他の事業者の大きな相違点でもある『自薦ヘルパー方式』(利用者自らが自分の気に入った人を選び派遣する方式)を導入している団体は73.3%を占めていた。積極的に『自薦ヘルパー方式』に積極的に取り組んでいるある団体では、「介助者の募集」や「面接の際に注意すること」「介助者との連絡方法」など段階的に個別に自立生活プログラムを行うなどの取り組みを行っていた。
また、夜間や急な介助依頼などに24時間携帯電話などで対応し介助者を派遣する『緊急対応』についても約90%の割合で実施されており、急な発熱や「ベッドから落ちた」などの依頼に介助者派遣を行っていた。
現在、医療従事者以外が行う行為としてグレーゾーンとされている『医療的行為』(褥瘡の処置や気管切開者のたんの吸引、摘便など)についても必要な介助として提供されている場合が多く、特に筋ジストロフィーなどの24時間介助を必要とする重度障害者の利用者が多いセンターでは、介助者に対する医療的行為の研修会が随時行われており、特別な介助ではなく日常的な介助として行われていた。
(3)自立生活プログラム開催状況
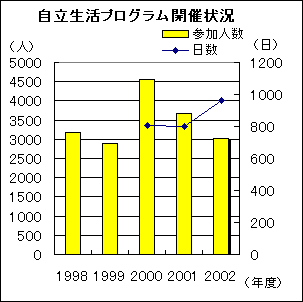 2002年度は特に、支援費制度開始に向けて個別対応の自立生活プログラムが多く行われていた。
2002年度は特に、支援費制度開始に向けて個別対応の自立生活プログラムが多く行われていた。
支援費制度開始に向けて、支援費制度の説明や支給量決定の受け方、介助の必要な時間や生活について見直すなどのプログラムが見られた。
知的障害の当事者リーダーの育成も進んでおり、知的障害者向けの自立生活プログラムを自ら企画・運営し「ガイドヘルパーと出かけたいところについて」「実際に出かけてみよう」などのプログラムが行われていた。
また児童向けのプログラムも行われており、障害を持たない児童と障害児の相互交流・理解を促すためのプログラム等も行われており、対象者やプログラム内容の幅も拡大されている傾向があった。
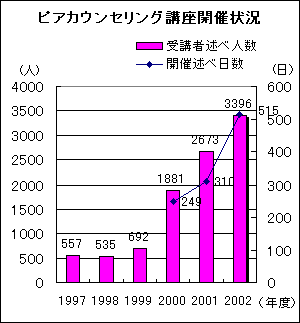 2002年度もピアカウンセリング講座の取り組みは進んでおり、参加述べ人数は3396人(前年度比:27%増)、開催延べ日数は515日(前年度比:66%増)ととなった。
2002年度もピアカウンセリング講座の取り組みは進んでおり、参加述べ人数は3396人(前年度比:27%増)、開催延べ日数は515日(前年度比:66%増)ととなった。
引き続き障害種別に対応できる講座の開催が進んでおり、聴覚障害者向けピアカウンセリングにおいては、専門用語や基本的なピアカウンセリングのルールなどについての講習が行われるなど、ピアカウンセリング講座に対応できる専門の手話通訳士の養成事業などが行われていた。
また療護施設などの障害者の入所施設へピアカウンセラーが訪問し、施設内での出張ピアカウンセリングなどの取り組みが見られた。
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
|
ピアカウンセリング講座 |
535 |
692 |
1,900 |
2673 |
3396 |
|
自立生活プログラム講座 |
3,175 |
2,885 |
4,647 |
3678 |
3028 |